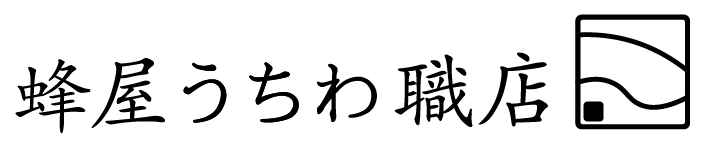
2025.1.31
vol.8 三竦み
正月前後にはその年の干支をモチーフにした品を作ることにしている。と言っても2024年の"辰"から始めたのでまだ2回目になるのだが。
"巳"の今年はどうしようかなと色々と考えた結果、蛇にまつわる言い伝えである「三竦み(さんすくみ)」をモチーフにすることにした。特にこれといった理由はない。なんとなく。
三竦み[さんすくみ]
(「関尹子‐三極」の「螂蛆食レ蛇、蛇食レ蛙、蛙食二螂蛆一、互相食也」による語) ヘビはナメクジを、ナメクジはカエルを、カエルはヘビを恐れるということ。転じて、三者が互いに牽制(けんせい)しあって、身動きできない状態をいう。
-精選版 日本国語大辞典 より-
ちなみに昨年の初回は龍をテーマにした品として「金銀雲龍図八角団扇」を制作した。団扇の形そのものは正倉院宝物にある鏡から、メインの龍と雲の図案は平安時代後期から、そして一部分だけ江戸時代の雲の図案を落とし込んでいる。
こういったアプローチをしていると、アーティストの創作というより編集者やDJなんかのような感覚に近いのかもなどと思うことがある。
ゼロから何を生み出すか、というより、どこから何を引っ張ってきてそれらにどう手を加えてまとまりのあるひとつの作品に仕上げるか、みたいな。
要するにミクスチャーですね。知らんけど。
今回の「金銀草花三竦図八角団扇」も同じアプローチを踏襲しようと考えていたので、全体の雰囲気は同じような品となっている。
三竦みが特に縁起が良いモチーフだというわけではないが、とりあえず蛇・蛙・蛞蝓なら他の図案は草花よね、という方針を決めてデザインを決めていった。
あとは鳥さん蝶さんにもゲストでお越しいただいたのだが、この2種類が加わるだけでグッと全体の感じが良くなったという手応えがあった。三竦みと草花だけだったある意味単調な雰囲気に少しの彩りを与えてくれたような感覚だろうか。
デザインに煮詰まっている時のちょっとした思いつきで試してみたのだが、我ながらグッドアテンドだったように思う。
尚、これらはほとんどが正倉院宝物に使われていたものなので、図案だけを見たら奈良時代で統一されている。図案の参考にするため手元にある写真資料を見る機会も多かったのだが、1200年前に作られた工芸品がこうして現存している事実に改めて驚きを隠せない。
というか、ちょっとした奇跡だとすら感じている。


ちなみに京うちわに関しては350〜400年前あたりに作られたものが作者(この場合は団扇面を描いた絵師)も明らかになった上で現存している。
絵師ではなく団扇そのものの制作を手掛けた当時の職人に関しては何一つわからないが、素晴らしい技術を持っていたことは資料の写真からでも十分にわかる。決して大袈裟に言うわけでもなく、今の自分では足元にも及ばないなと痛感する。
名ではなく品を残し、残した品で語る。
ひとりの職人として、単純に格好良いなと思う。自分にもこれができたらなとも強く思う。
こういった経緯もあり私 蜂屋には「400年後まで残る品を生み出す」という職人としての人生をかけた野望がひとつある。(他にもいろんな野望あるけど)
そしてこれは全くの感覚的かつ無責任な話にはなるが、今の自分に100年後200年後まで残る品を作ることはできるように思う。上に載せた大物2つも200年後にどこかで残っている可能性はそこそこある気がする。
ただこれが400年となると、ちょっとしたもん作れますよ、みたいな小手先の技術だけではおそらく到底無理な話で、素材や技法への本当の理解と、それらを体現する洗練された技術が必要になるだろう。あとはもちろん、美的センスも。(重ね重ね言うが全く根拠はない)
そういったことを考えるほどに、自分はまだ何もわかっちゃいない、という実感は強い。
先に述べた正倉院やらの話もそうだが、時を超えて人の心を震わすものの力を信じているし、そういったものと遥か彼方の繋がりを信じている。
自分が死んだ後の世界のことをあれこれ言うのはある意味無責任だけど、そのずっと後の世界に何かひとつでも残せたら、という思いはきっとこれからも大きくなるだろう。
「待ってろ未来人」とたまに冗談半分で使ったりするけど、あとの半分は本気だよ。待ってろ未来人。