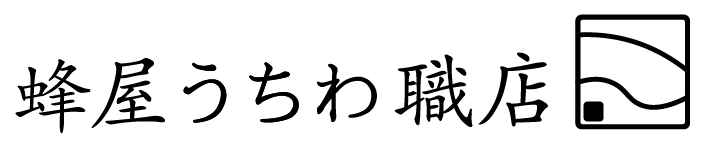
2025.3.21
vol.15 陰翳について
近頃は改装に関しての半ば手を抜いたコラムで済ませていたので、こうして普通の文を書くのは久しぶりな気がする。
ただこの流れで書かないと今後触れることもそうないと思うので、ついで広くなった空間に関してちょいとだけ。
今回の改装では畳3畳分+αくらいの空間が新たにできた。3畳と聞くとそんな大したことないやん、と思うかもしれないが案外広く感じるものである。ちなみに京間だったので少し得した気分。
その畳の間には意図的に照明を設けておらず、自然光のみの採光としている。
めっちゃ暗い、というわけではないが、現代日本の一般的な住まいの明るさと比べたらそこそこ薄暗い空間には感じられるように思う。
そしてこの「薄暗さ」は正直自分が欲していたものであるし、照明を設けないことにも明確な理由がある。
-
諸君はまたそう云う大きな建物の、奥の奥の部屋へ行くと、もう全く外の光りが届かなくなった暗がりの中にある金襖や金屏風が、幾間を隔てた遠い〃庭の明かりの穂先を捉えて、ぼうっと夢のように照り返しているのを見たことはないか。その照り返しは、夕暮れの地平線のように、あたりの闇に実に弱々しい金色の明りを投げているのであるが、私は黄金と云うものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。
- 谷崎潤一郎「陰翳礼讃」より
この文が全てを語っている。暗闇での金銀箔が最も美しく見えるのだ。
最近は金銀箔を施した飾り用の美術品に近い団扇を意識的に作るようにしているのだが、それらを扱っていく中でもこのことをより強く実感するようになった。
夜に金箔を施した団扇の側を歩く時、ゆっくりと変わっていく金の表情は確かにこの上なく美しい。自分だけが知る美しさであるとも思う。なので金箔を使った団扇を買われた方には「夜がいちばん綺麗なので、ぜひ見てみてください」と伝えるようにしている。
そういった部分を掘っていくと、日本の住宅空間について、蝋燭・ガス灯・電気灯など照明の変遷について、そしてそれらと密接に関わっている日本人の美的感覚についてなど話の広がりが留まるところを知らないが、そのあたりは谷崎が全部書いている。「陰翳礼讃」まごうことなき名著であると思う。未読の方はぜひ。マジで。
話が少し逸れたが、うちの店の新しい畳の間はそのように金銀を美しく見せるための空間としているよ、という事をここに書いておきたかった。以上。という雑な締めとさせていただく。
ちなみに谷崎はベタに「痴人の愛」から入って「細雪」「蓼食ふ虫」「刺青」「卍」など有名どころは大体読んだが、「春琴抄」が好きだったような記憶がある。
けど京都に十数年住んだ今になって「細雪」を読み返したら、きっとイメージがより鮮明に浮かび、当時とはまた違った面白さを感じるんだろうなとも思う。